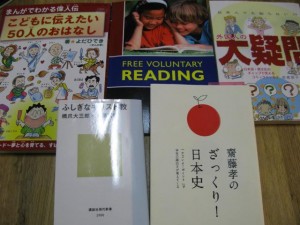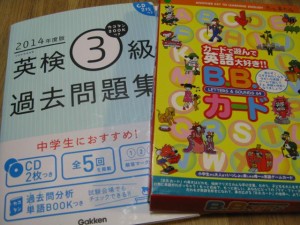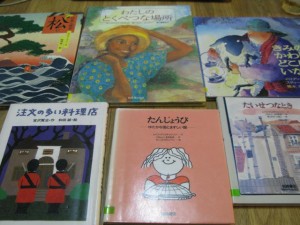春です。
卒業の春。入学の春。新しいスタートを迎える春。
昨日の回覧板の中に、地元の小学校と中学校の卒業記念広報が挟んでありました。「未来の自分」、「将来目指す人物像」というページに目が止まりました。
「未来の自分」は、保育士、看護師、サッカー選手、ペット屋さん、宇宙飛行士など。時代を反映してか、中にはYoutuberになりたい!など、興味深い未来像もありました。それぞれの夢が叶うといいなあと思って読みました。
「将来目指す人物像」の中には、エジソン、坂本龍馬、オバマ大統領、高倉健、ウォルト・ディズニー、錦織圭など。歴史的な人物、今旬の有名人があげられていましたが、中には担任の先生の名前を書いていた人もいました。この先生はきっとみんなから慕われていたんだろうなーと思いながら、あたたかな気持ちになりました。
私も小さい頃、憧れていた職業がありました。
「先生」です。
いま、曲がりなりにも「英語の先生」というお仕事をさせていただいていますが、子どもの頃、ぼんやり思い描いていた「人物」になれているのかなあと、ふと考えました。
何かに「憧れる」ということは、とても大切だと思います。「憧れる」という思いは人を突き動かします。
小さな町の英語の先生として、子どもたちに伝えたい、大切なことがあります。
「英語がわかったり使えるようになると、自分の可能性がさらに大きく広がるんだよ。」というメッセージです。
英語はことばです。ことばは「自分と周りをつなぐツール」です。
「聞く」「話す」「読む」「書く」という具体的な4つを考えてみても、自分が周りとつながり、理解し合い、助け合い、生きて行くためのたいへん重要なスキルです。
日本に住んでいる私たちは、まず日本語が大切なのですが、日本と世界がこれだけ近くなっている今、「日本語だけやっていれば」という時代でもなさそうです。世界のいろいろな国、人、ことばに興味を持ち、母語以外の言語や文化について学ぶことは、日本が世界と共に生きて行くためにとても大切なことだと思います。
家の小さな英語教室で教えながら、ここ数年、日本の英語教育に関して、試験偏重の「英語教育」に関して、危惧している自分がいます。
小学生のあいだは、のびのびと自由に「ことばとしての英語」を吸収できていた子どもたちなのですが、いったん中学校に入学すると「テストで点がとれるように」という心配が始まります。英語に対して萎縮しはじめる子どもたちが出てきます。成績として評価される英語になってしまうことが残念でなりません。
評価される科目としての「英語」になってしまうと、とたんにそれは辛く、つまらなくなります。
ことばが使えるようになるためには「憧れ」「興味」「好奇心」がとっても大切です。
「成田を歩いていたら、外国人親子の英語の会話が耳に入ってきて、内容少しわかっちゃった。」
「おさるのジョージは超可愛い。ジョージを思う黄色い帽子のおじさんのセリフがいい〜。」
「One Directionの新曲のフレーズがしびれる〜。」
「アナと雪の女王の”Do you wanna build a snowman”を歌えるようになりたいな〜。」
どんなことでもいいのです。実際に英語を使ったり、聞けたり、歌えたり、いろいろなことに憧れて、それをやっている自分を想像してみる、そうすることで、英語が「お勉強する科目」ではなく、「やりたいことが可能になるツール」になっているのですから。
テストでどんなに良い点が取れたとしても、使ってみなくちゃおもしろくありません。実際、「英語の成績は良かったけど、使うとなるとなかなか難しい。」という話しはよく聞きます。
どうしてなのでしょう?
それは、とっても貴重な中高6年間、試験偏重の英語のお勉強ばかりして、英語を使ってみる機会が、あるいは英語を使ってみようと余裕を持ってかまえる時間がなくなってしまうからなのかもしれません。
「日本にいたら身近で英語を使う機会なんて、そんなにないですよ。」という人もいるでしょう。
ほんとうにそうでしょうか。
インターネットがこれだけ普及した時代、クリックひとつで、自分と世界が繋がります。英語ひとつをとってみても、映画、ドラマ、ニュース、音楽、遊びに関するあらゆる情報がリアルタイムで入手できます。アメリカ英語、イギリス英語、オーストラリア英語、インド英語、アフリカ英語、英語圏の国だけにとどまらず、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、世界のあらゆる国々と、英語を介して繋がることが瞬時にして可能な時代に私たちは生きています。
英語を使ってみる環境は皆さんの周りにあふれています。大好きなおさるのジョージの英語版を、Dr.スースの児童書を原文で読み始める瞬間から、英語を使っているあなたがいるのです。
好きなことはありますか。憧れていることはありますか。
英語が「お勉強としての教科」ではなく、「憧れや夢を実現させるためのツール」になるとき、皆さんの世界は変わっていくはずです。
私は高校生の頃、この方に憧れて、卒業後渡米しました。自転車のかごの中でかっこいいでしょ!
アメリカに行ったらE.T.に会えるかもしれない、と思っていたのです。
半分冗談ではありますが、中高生の頃、父とよくクリント・イーストウッドやロバート・レッドフォード主演の映画を見に行ったり、E.T.をはじめとしたスピルバーグのサイエンスフィクション、カリフォルニアの学園ものの映画に憧れて、「あの国に行ってみたいなあ〜」と思っていました。
卒業式の二日後にはアトランタ行きの飛行機に乗って旅立って行きました。30年前のことです。
アメリカ留学時代はいろいろな体験をしました。
もちろん生活に慣れるまでは大変なこともありましたが、「あこがれ」が自分を突き動かしていたので、勢いがありました。それまで思い描いていた夢や好奇心がひとつのかたまりとなって、どんどん突き進んでいた自分を思い出します。
あなたが「憧れ」ていることは何ですか。
この春、英語を使う生活をはじめてみませんか。
外国に行かずとも、留学しなくとも、リアルタイムで英語を使うことは誰にも可能な時代になったのですから。
☆ランキング参加中☆
ボタンにクリックをよろしくお願いします♪